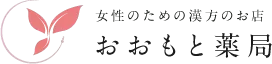更年期障害に良い漢方薬
前回の更年期についてのブログでは「当帰」「阿膠」など更年期に重要な生薬についてお話しさせていただきました。今回はそのほかの生薬や、漢方処方についてお話しさせて頂きたいと思います。
まずは「プラセンタ」について、プラセンタと聞くと、漢方薬を連想する方は少ないと思いますが、このプラセンタは哺乳動物の胎盤を乾燥して得られたエキスで、漢方の世界では、古くは700年代から中国で使われており、明の時代には「紫河車」という名前で、治療に用いられてきた記録が残っています。
中国では秦の始皇帝が不老不死の妙薬の一つに用いたと言われています。唐の時代には「本草捨遺」(ほんぞうしゅうい)という書物の中で紹介されていて、明の時代には「本草綱目」という書物に「紫河車」の名で登場し、肉体的、精神的な疲れに効果があるとして、滋養強壮的な漢方薬として重用されていたようです。楊貴妃もこの「紫河車」を服用していたと伝えられています。現代でも漢方の世界で欠かせないものです。西洋でも、古代ギリシャの医師で西洋医学の父と呼ばれるヒポクラテスが治療に使用していたと言われています。エジプトの女王クレオパトラやフランスのマリーアントワネットが若返り、美容の目的で利用していたことは、色々なところで伝えられ、有名です。
そもそも「プラセンタ」(紫河車)とは、哺乳動物の胎盤です。「胎盤」は胎児をお腹の中で育てるための栄養が蓄えられており、胎児の生命を維持し、成長させる大切な働きをしています。現在では医療機関でもプラセンタ注射としてヒト胎盤の製剤が使われています。また内服では豚胎盤から抽出したエキスが市販されています。
プラセンタ注射の効能としては、更年期障害と肝機能疾患となっていますが、様々な効果が実証されています。ただし、プラセンタ注射はヒトの胎盤から作られていて、1度でも注射を受けると献血をしてはいけないとされています。一般に市販されているプラセンタはほとんど豚の胎盤から作られており、内服ですので安心してお飲みいただけます。
プラセンタ注射の有効な疾患や症状としては、更年期障害、肝機能障害はもちろんの事、頭痛、口内炎、気管支炎、喘息、胃弱、肩こり、筋肉痛、関節痛、神経痛、外傷、手術後の創傷治癒、下肢静脈瘤、乳汁分泌不全、生理痛、生理不順、冷え性、皮膚炎、しみ、乾燥肌、自律神経失調症、うつ、不眠、不安症、パニック障害、前立腺肥大、めまい、鼻炎、などなど様々な効果を期待されています。
注射程の効果は期待できないにしても、安心して飲むことが出来る、内服のプラセンタにも似たような効果が期待できます。
西洋医学では1つの物に、このように多様な効果があるという事は考えにくいですが、このプラセンタを漢方薬の「紫河車」として昔の人がどのような人に使っていたかを考えるとまず
①男女問わずの虚労(疲れ切っている状態)
②婦人骨蒸労損(出産のより体力を消耗しきってしまった状態や、結核、肺病、更年期症害など)
③五労七情による吐血や羸痩(肉体的や精神的ストレスにより、血を吐いたり、痩せてくるほどの衰弱)
というように、ひどく疲れ切ったり、衰弱した状態の時に服用し、回復を助けたのだという事がわかってきます。ですから多くの効能があるというよりは、弱っている状態から回復するのを助ける働きをするのだという事がわかります。現代的な言葉に置き換えると、弱った組織を修復したり、不足した成分を身体が作れるよう力づけたり、自然治癒力を高める働きが期待され、
〇内分泌調整作用
〇基礎代謝向上作用
〇自律神経を整える
〇免疫を刺激する
〇肝臓の働きをたすけ解毒作用を強化
このような働きが考えられ、又実証されています。更年期障害に
最適なプラセンタ(紫河車)であると言えると思います。
このプラセンタ(紫河車)は上述のように内分泌調整作用を持っていますので、更年期障害の原因であるエストロゲンの低下によるホルモンバランスを少しでも助ける働きが期待できます。また、エストロゲンの低下による自律神経の不調にも対応して、衰えていく体力を少しでも助けていく事が出来ることから、更年期障害には最適な生薬であると言えます。さらに、当店の商品である、「王妃アキョウ」には東亜県産の純度の高い「阿膠」を配合しており、更年期の不正出血や、骨粗しょう症、関節痛、肌の衰え、目や肌の乾燥、シミなど老化の始まりである更年期による障害にお役に立つ商品となっています。更年期に限らず産後や子宝、美容にとすべての女性に、お役に立てていただきたい商品です
実際、当店のお客様では、更年期でなんだか気分も鬱々としていたのだけど、この「王妃アキョウ」を飲んで2か月くらいたつ頃から、身体も元気になり、気分も晴れやかになった。3~4か月飲んだ頃から足腰の痛みが楽になって、出かけるのが楽しくなり、更年期の症状は多少あるけれど、元気になった気がするなど嬉しい感想をいただいています。
次に、更年期障害によい漢方処方についてお話ししたいと思います。
更年期障害には「加味逍遙散」とよくいよく言いますが・・・・・
もともとこの「加味逍遙散」という処方は、加(加える)味(薬味)という文字がついており、元々の「逍遥散」という処方にさらに薬味を足した処方でありそれが、牡丹皮と山梔子という生薬になります。まずは元々の「逍遥散」という処方についてお話ししたいと思います。この処方は和剤局方という書物の婦人病のところに出てくる処方です。この処方は血虚の人に使う処方であり、血虚とは血液も少ないしホルモンも少ない、しかも血液の流れ、血行とホルモン分泌が不良であることを言います。この血虚の人が無理をして仕事をすると、まず心臓に疲れが出てきてそれにより血管に影響が現れ、手のひら、或いは足の裏にポーっと熱っぽい感じが出てきます。これを漢方では血熱と言います。もちろん心臓が疲れて胸苦しい感じがしてきます。そしてこのような血熱の症状から、口が渇きやすいという症状の出る人もあります。そして、疲れが重なると体力の低下から、胃腸の調子もよくない、又血液に関係のある、月経も整わなくなってきて、下腹も張ってくる、時には午後になってポーっと熱っぽくなってくるなどの症状が出てきます。つまり血虚、ホルモン不足による症状がこのような症状になり、この「逍遥散」が適していると言えます。この「逍遥散」という処方には、血液に効果のある「当帰、芍薬」で血行、神経の鎮静の働きをし、「柴胡」でもって、肝臓からくる疲れストレス、鬱血に効果があり、午後からだるくなって熱っぽくなるという症状を解消してくれます。そして「薄荷」により気持ちをスッキリとさせてくれます。さらに、「茯苓、白朮、甘草、生姜」というグループが胃の調子を整えてくれ自律神経の調整にも役立つという働きを持ちます
そしてこの「逍遥散」に牡丹皮、山梔子を加えたのが加味逍遙散なのですが、この2つの生薬は特に散剤で使う場合は煎じるのではなく、生薬を末にしたものを加えますので大変胃に障ってきます。ですから私はこの「加味逍遙散」という処方は、ほとんど使わず、「逍遥散」という処方を、四物湯加減という処方に合わせてお飲みいただく事が多いです。
「逍遥散」の他にも当店では
四物湯加減+α(逍遥散、四君子湯、六君子湯、平胃散)温経湯、当帰建中湯、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸料、折衝飲、ケイギョク膏、などなど様々な処方の中から、お客様に最適な処方をお選びするよう心がけています。
更年期障害は40代後半から50代前半にかけて個人差はありますが、ほとんどの方が経験する症状です。更年期だから仕方がないとあきらめないで、少しでもこの期間を快適に過ごせるよう、漢方薬の力を信じて試してみてください。更年期は老年期の始まりです。このころからコレステロールや中性脂肪の上昇、骨粗しょう症の始まり、関節軟骨の減少や筋肉の低下による足腰の弱りなど様々な症状を表してきます。漢方薬にはこの老化の進行を緩やかにし、健康な老年期に向かっての準備をするのを助ける力があります。5年10年と経つうちに、飲んでいる人と飲んでいない人との間には差がついてくると思います。もちろん日々のバランスよい食事や、運動による差は大きいです。歳をとるのは仕方がないけれど、健康で楽しい老年期のために、是非漢方薬をお役立てください。
メールでのお問い合わせはこちらから Lineでのお問い合わせはこちらから オンラインショップはこちらこちらから